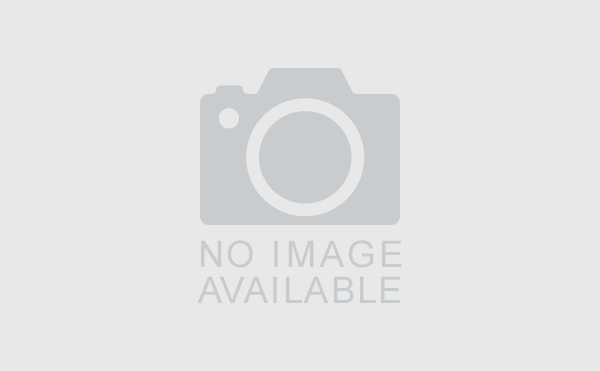◇7、8年ほど前、デジタル教科書が、数年後に日本でも導入されると言う時に、テレビ局の取材を受けた。
そして、その当時「NEWS ZERO」や「スッキリ」という番組で、
私のインタビューが流れたのだが、90分のインタビューで私が力説したこととは、
全く違う箇所が切り取られて流されていた。デジタル教科書は面白い!という文脈だった。
iPadを渡され、実際に使ってみて、子どもたちもこれを操作するのは
面白いだろうなということを言ったのだが、ここを使われてしまった。
◇私が力説したのは、まず、「学びは、人と人の間にある」ということだ。
何かを知るためには、誰かの話を聞き、誰かの書いたものを読み、
誰かと話しながら身体的に知識をつかみ取っていくものだから、
デジタル教科書では学べないということを言ったのだ。
◇そして、次に、わからない単語や語句は、デジタル教科書では、
その中で完結してしまって(単語や語句をクリックすれば、簡単にそこに飛び、解説がある)、
調べるという行為に、苦労がないということだ。
誰かに聞くこともないし、何かを使って調べることもない。
デジタル教科書の中で、すべてが終わってしまうのだ。
◇そして、最後に、学びための作業がない。見て終わるということだ。
書いて覚えるとか、記憶するために書くとか、
知ったことを整理するために書くとか、そのような作業がないということだ。
学びが身体を使って行われないということだ。
◇デジタル教科書がダメな理由を山ほど言い立てたのだが、
その当時のインタビュアーは、全く聞く耳を持たなかった。
新しいことが何でもかんでも良いということではない。
時流に合ったことが良いということでもない。
人間は、身体性を抜きにしては語れないものだ。
子どもが大人になっていくということも身体性の問題が根本なのだ。
そのことを忘れた教育議論は、非常に危ういと私は思う。
デジタル導入の「教育先進国」で成績低下や心身の不調が顕在化…
フィンランド、紙の教科書復活「歓迎」
(読売新聞3月18日)
〇デジタルを積極導入した海外の「教育先進国」で、
子どもの学力低下や心身の不調が顕在化し、見直しの動きが相次ぐ。
反対に日本は、学校教育の根幹にある教科書を、
紙からデジタルに置き換えようと突き進む。
文部科学省が主導する推進議論の危うさを指摘する。
〇人口556万人の北欧フィンランドは、
教育を柱とした人材育成に国家の命運を懸けてきた。
大学を含む学校の授業料は無料で、小学校以上の教員は修士号を持つ。
教育現場へのデジタル導入は早く、1990年代から進められてきた。
〇2000年に始まった国際学習到達度調査(PISA)で、
フィンランドの子どもの読解力は世界一だった。
03年に数学的応用力、06年からは科学的応用力も
PISAで本格的に測られるようになり、初回は2位と1位。
好成績の理由を探る各国の「フィンランド詣で」が続いた。
〇だが22年には、3分野の順位が14位、20位、9位に落ちた。
「教育は、急速なデジタル化に対応できるものではなかった」。
アンデルス・アドレルクロイツ教育相(54)は述懐する。
〇首都ヘルシンキ近郊の小都市リーヒマキは、
同国内でも教育のデジタル化に先進的に取り組んだ自治体。
約10年前から中学生の1人に1台ノートパソコンが配られ、
デジタル化した教科書や教材が多用されてきた。
〇だが2月下旬、市内のハルユンリンネ中学校を訪ねると、
教室の風景は変わっていた。「みんな、文法のページを開いてください」。
2年生の英語の授業で、生徒たちが手を伸ばしたのは、パソコンではなく紙の教科書。
解説を読んで理解した後、鉛筆やペンで問題プリントに答えを書き込む。
リーヒマキでは昨秋、中学校の英語を含む外国語と
数学の授業で使う教科書が、デジタルから紙に戻されていた。