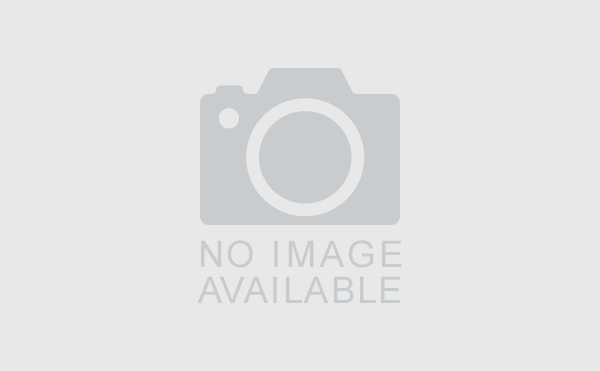◇1970年代、日本の教育界は、真摯な議論をしていた。
「関心・態度」という観点で成績を付けるのは、教師の主観によるところが大きいから、
学習指導要領に載せるべきではないという議論があった。
子どもたちの内面の評価を一個人である教師がするべきではないという議論もあった。
しかし、1980年、学習指導要領に「関心・態度」が観点の最後に載ったのだった。
そこからは、皆さんの知っての通り、どんどん幅を利かせ、
1991年、「関心・意欲・態度」として、観点の最上位に置かれることになる。
認知面の評価が主に「知識・理解」、情意面の評価が「関心・意欲・態度」として、その情意を最優先することになったのである。
70年代の議論は全く生きることなく、日本の教育は、この1991年を境に、どんどん悪くなっていったのだ。
◇そして、今回の記事である。
教師の負担から、見直しを検討しているということだ。
子ども不在の見直しということだ。
子どものための評価を、教師の業務負担の目線で見直すというのだ。なんとふざけたことだろう。
1970年代の日本の教育行政に携わっていた人たちは、今回の記事をどう思うだろう。
あの時の真剣な議論を忘れたのか、そう思うのではないだろうか。
私たちは、思い出すべきだ。日本も、教育について真剣に考えていた時期があることを。
◇子どものために、どんな評価が客観的で、公平なのかを議論することだ。
ここからしか、日本の学校教育は、良くならないのではないか。
+──────────────────+
通知表が変わる? 学習態度は成績に反映せず所見に 歓迎の教員も
(朝日聞7月4日)
〇小中高校の子どもの成績のつけ方を見直す案が示された。
各教科で「5」などの成績をつける際の観点の一つとなっている「主体的に学習に取り組む態度」について、
数値には直接結びつけず、所見欄で評価を書く形に変える。各校が作る通知表も変わりそうだ。
〇文部科学省が4日、中央教育審議会(文科相の諮問機関)の特別部会で提案した。
今の方法は、各教科ごとに「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の三つの観点をABCの3段階で評価。
それを総合し、各教科の成績にあたる「評定」を決めている。小学校は3段階、中学高校は5段階が一般的だ。
〇このうち「主体的に学習に取り組む態度」は客観的な評価が難しく、
ノート提出や授業中の挙手の回数などでみる教員も少なくない。
「形式的な評価」という意見も出ていた。
このため文科省は、成績には直接反映させず、所見欄に評価を書く方法を提案。
特に良い場合は「○」をつけるなどし、成績評価の補助的な材料にするとした。
〇文科省の案は、各校に作成・保管の義務がある「指導要録」への記録が前提で、各校が独自に作る「通知表」とは違う。
ただ、双方とも要素は原則同じなので、通知表も変わる見込みだ。
〇今回の案は、2030年度にも予定される学習指導要領の改訂にあわせて導入される予定。
また文科省は、成績をつける頻度を減らす案も示した。
学期ごとに通知表で示すのが一般的だが、学年末のみにすることで、
成績をつける教員の負担を減らしたり、子どもの年間の成長をより柔軟に評価したりできるとした。
成績をつける回数は減らすが、学習や授業の改善のための日々の振り返りを充実させるのは重要だとした。
〇ただ、学年途中の習熟度が分かりづらかったり、
中3は高校入試向けに2学期までの成績が必要だったりする課題もある。
詳細について検討を続ける。