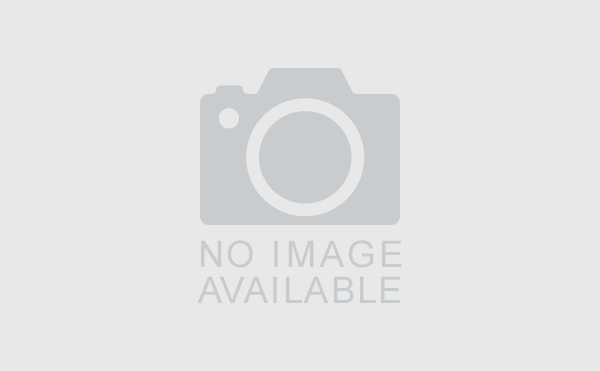◇私は、2020年スタートの学習指導要領に大きな不安を持っていた。
「思考力・判断力・表現力」をつけるという無理な目標に不安を持っていたのだ。
思考力や判断力が、学校教育の中で本当につくかどうか、非常に疑問なのだ。
問題を考えるスキームを教えないで、思考力をつけることは難しい。
ましてや、義務教育の年齢の子どもに、まず、基礎基本の知識を徹底的に教えないで、
どうしてその先に行けるのか?誰でもが疑問に思うだろう。
◇なんでもそうだが、自分のやることが好きなことが一番生き生きするはずだ。
勉強だって、好きにさせることが重要なことなのに、その好きにさせる構造を考慮せず、
「思考力・判断力・表現力」と言ってみても、無理だ。
そうそう簡単に、現実的な思考なんぞ出来るわけがない。大人だって出来ないのに。
◇この記事にあるように、問題は教科書の中身ではない。
その中身を規定している学習指導要領が問題なのだ。
まず、知識・やり方を教える。そして、その知識ややり方をその他に転用できるように教える。
最後に、思考力・判断力が鍛えられるようなテーマを設定し、子どもたち同士で学び合う。
そのようなプロセスを考えることだ。小学生や中学生のうちから、
「思考力・判断力・表現力」などというカッコよいお題目を設定することはないのだ。
世界中の状況を見てほしい。「思考力・判断力・表現力」をもって行動している人間(国民)がどのくらいいるのか。
日本の教育が世界から遅れていると思ってはダメだ。
だから、この学習指導要領にしたのだ、などと思わないことだ。
そうではなくて、このような学習指導要領が日本の教育を遅れさせていると思った方が良いと私は思う。
分厚い教科書にうなる子ども
教員らが洗い出した「不合理な内容」
(朝日聞7月11日)
〇小学校の先生が、分厚い教科書から、不合理な内容を洗い出す──。
そんな発表が6月末、都内で開かれた公教育計画学会であった。
北海道妹背牛(もせうし)町立妹背牛小学校教諭の水本王典(きみのり)さん(57)と
兵庫県芦屋市立小学校を退職した元教諭の永田守さん(58)が、
それぞれ3年生の算数と国語の教科書について、世代の違う教員と計3人ずつで分析した。
〇まず、水本さんが紹介した算数の問題の一つが、
「20cmのリボンがあります。20÷4の式になる問題をつくりましょう。
また、答えのもとめ方を、図を使ってせつ明しましょう」。
〇説明、説明、説明……。今の学習指導要領は「思考力・判断力・表現力」を重視し、
教科書もあちこちで子どもに説明を求める。
「子どもは苦しんでいます。まずわかればいいと思うのですが」と水本さん。
〇国語も「表現力を重視し過ぎです」と永田さんは話す。
例えば、「働く人々の仕事の工夫を調べ、報告文を書く」。
ここでピタッと手が止まる子がいる。「うーん」とうなる子も。
仕事の選び方や報告文の書き方に悩んでいるのだ。
〇そして最後は、発表し交流する会を開くことになっている。
「会を開くために、全員が報告文を完成させなければならなくなる」と永田さんは言う。
昔話の教材も、以前は読み合い、ワハハと笑って終わりだった。
それがいまは、「昔話の組み立てをとらえよう」。
永田さんはため息まじりに話した。
「これでお話が大好きな子どもが育つでしょうか」
〇この6日前、次の指導要領を審議する中央教育審議会の部会が開かれた。
ここでも教科書の分厚さや、教科書を網羅的に教えなければならないと考える教員の姿勢が議論され、
「中核的な概念をつかみやすいよう重点化する」方針が出された。
〇だが、水本さんと永田さんは、子どもを混乱させる指導要領が問題で、
教科書はそれに合わせようとしているだけだ、という。