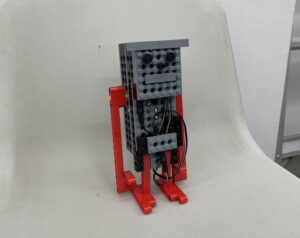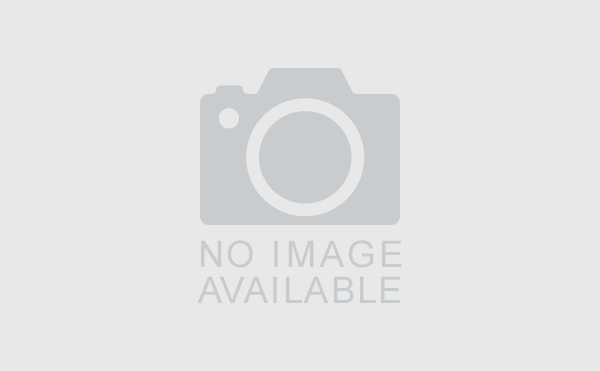◇シンプルに考えれば、学習塾も客商売です。
ただし、客商売にしては珍しく、お客=子どもを指導することで、対価を頂いている指導業です。
ここがほかの客商売とは違うところです。
そして、それは、同じ指導業としての自動車学校とも違うところです。
◇それは、なぜか。自動車学校は、資格を取れば、それでお仕舞ですが、
学習塾は、成績を上げても、高校入試に合格しても、その先まで原理的にはお客が残っていくことを許すものだからです。
学習塾に通うのは、明確な目的のために通う自動車学校とはちょっと違うのです。
◇それでは、なぜ、明確な目的がなくても子どもたちは学習塾に通うのでしょうか。
また、保護者はなぜ、自分の子どもを学習塾に通わせるのでしょうか。
それは、漠然とした不安が潜在意識の中にあるからです。
そして、その漠然とした不安を解消してほしいと願うからです。
◇「このままでは、学校の成績が落ちてしまうのではないか。」、
「このままでは、高校に入れないのではないか。」、
「うちの子は、他の子どもとやっていけるのだろうか。」、
「勉強はついていけているのだろうか。」
このような漠然とした不安が、学習塾に行く動機になっているのです。
ですから、明確な目的、例えば、「英語を80点にしてください!」と言わずに、
「できれば80点ぐらい取れないと大変ですよね」なんて、保護者は、お茶を濁すのです。
ここに、学習塾の難しさがあります。
◇この漠然とした不安が、子どもに対する指導を非常に難しくさせているのです。
そして、指導業としてのあり方が、更に事態を難しくさせます。
生徒や保護者の漠然とした不安を明確にしてあげようとする余り、
「こうあらねばらない」とか「ここまでする必要はない」とか「自分の信念にそって指導をする」とか、
そういう独善的なあり方が簡単に出てきてしまうのです。
誰のために、何のために指導をするのか、最初は、生徒のために、保護者のために、という意識が、
結局、自分の自己満足に陥ってしまう危険性があるのです。
◇ですから、いつでも私たちが考えなければならないことは、
自分のやっている行為や思いは、自分の満足のためなのか、それとも相手の満足を引き出すためなのか、ということです。
そういう意識がないと、私たちはすぐに、自己満足的な行動や思いに陥ってしまいます。
こういう塾が、案外多いのです。
◇どうしてそうなってしまうのか。
それは、先述の曖昧な不安ともう一つ、子ども相手だからです。
大人の目で見られているという意識がないからです。
つまり、対等な意識が生まれにくいのです。
「子どもだから、自分の方がなんでも知っているはずだ。」とか、
「子どもだから、そんなことまで思わないよ。」とか、
「この程度のことなら子どもは許してくれるだろう。」とか、そういう甘えがあるからです。
ついつい自分の都合に合わせて、仕事をしてしまいがちになるのです。
これは、自分の満足を考えてしている仕事以外の何物でもありません。
だから、塾の先生も学校の先生も自分の好きなことにしか興味や関心がないことが多いのです。
子どもたちが将来生きるであろう社会のこと、人間のことを知ろうとしないのです。
先を予測できない人間でも良いと思っているのです。
それでは、子どもを導くことはできないのではないでしょうか。
◇この意識を変えることです。
そうすれば、私たちの仕事の質は大幅に向上し、生徒や保護者から厚い信頼を得ることができるはずです。
なぜならば、相手の満足を高めようとする意識で、行動をするからです。
私たちに大切なことは、この相手の満足を引き出す行為です。
ですから、相手に迎合することなく、自分の都合に迎合することなく、相手の満足を引き出すために、行動をしていきましょう。
それが、指導業としての学習塾の姿勢だと思います。
子どもが将来にわたって、あの塾に出会えてよかったと思ってもらえることこそ、学習塾が目指すべき満足です。
ユニバ進学教室は、大阪府豊中、招堤、石切、瓢箪山、宮之川原、平野、島本、放出東にある個別指導塾です。教えすぎず、自立させ、成績アップを目指します。
お気軽にお問い合わせください。0120-588-761受付時間 9:30-20:00 [ 土・日・祝日除く ]